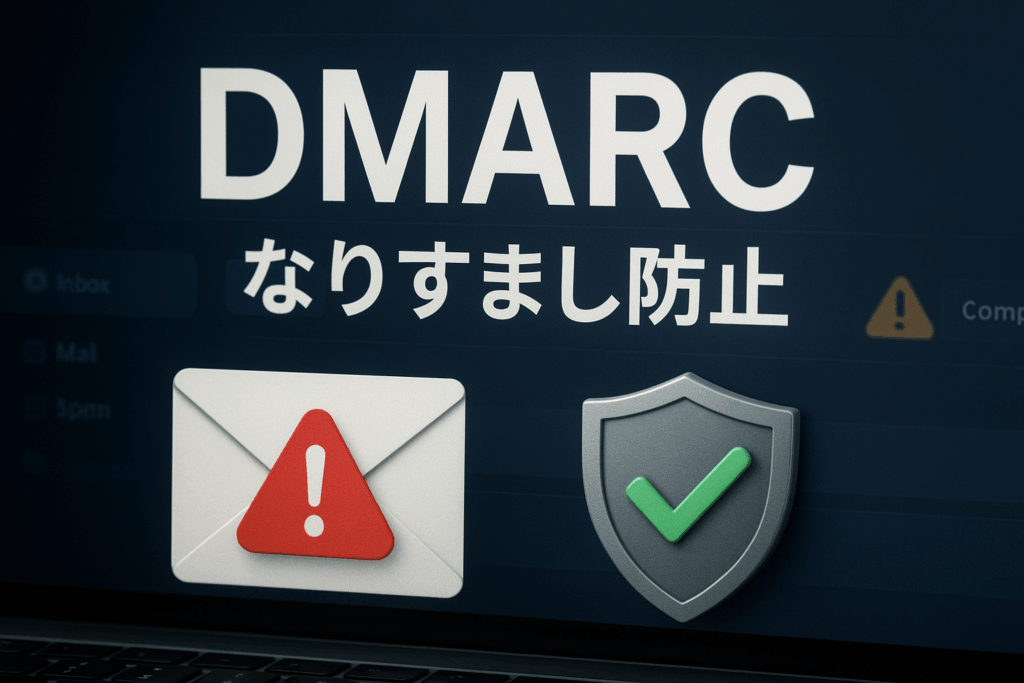サイト運営について基本的な方針(気になったことを書いていく)の変更はありませんが、 サイトに広告を配置して収益を得る検討をしてみようと思います。 記事については 何か依頼があり面白そうなら書いてみるという程度のスタイルは変えないので、いいことを書いてもらおうと依頼されても製品自体がいまいちならご期待の内容にならないのでその点はよろしくお願いします。 今回の検討は、記事の上下左右に自動で埋め込まれる広告です。 20年くらい前に試行して、月当たり千円程度の収益が上がっていた時期もありますが、サーバシステム更改のタイミングで、広告掲載をやめていました。「Google AdSense」 を試してみます。
収益の推定 手間もいろいろかかるので、その程度の収益になるかを推定してみます。
5年間のトップページアクセス数から推定した結果は次の通り。 サーバ統計でのページビュー数より推定 かなり幅はあります。
MIC-NETの推定は置いておいて、他のサイトはどうなのか見てみました。
例1:新潟県 新潟県は自治体で初めてGoogle AdSenseを導入した事例として知られていますが、現在は固定型・変動型のバナー広告をトップページなどで掲載し、財源確保を図っています。
広告導入基本方針: https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/ict/1228420866024.html
トップページ(広告表示例): https://www.pref.niigata.lg.jp/
例2: 姫路市(兵庫県) 例3: 岸和田市(大阪府) 公式ウェブサイトにバナー広告を募集し、財政収入の確保と地域産業振興を図っています。月平均アクセス数に基づく掲載。 URL: https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/3-banner-ad.html 例4: 名古屋市(愛知県) 公式ウェブサイトのトップページおよびサブトップページにバナー広告を募集・掲載。 URL: https://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000089829.html 例5: 札幌市(北海道) 公式ホームページにバナー広告とテキスト広告を掲載。サイズ拡大により視認性を高めています。 URL: https://www.city.sapporo.jp/city/ad/boshu/index.html 例6: 栃木県 ホームページに10枠のバナー広告を募集・掲載。 URL: https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/kensei/kouhou/hp/banner.html これらの事例は、自治体の財政難対策として増加傾向にあり、広告掲載により月数万円から数十万円の収入を得ているケースが多いです。AdSenseに特化した最近の事例は少ないですが、上記のバナー広告が主流です。詳細は各URLで確認してください。
まとめ その他、企業のサイトについていくつかのサイトについてみてみましたが、広告自体をサイト運営団体が直接受け付け掲載しているケースがほとんどで、AdSenseなどに広告掲載を外部丸投げしているところはほとんどなさそうです。
25年ほど前に、mic.or.jpで一時期広告を掲載していました。当時は数千円/月程度の収益で、サイト運営のささやかな支えになっていました。しかし、システム更新のタイミングでユーザー体験を優先し、広告を外してしまいました。最近、サイトの成長とともに「持続可能性」を再考する機会が増え、再び収益化を検討中です。この記事では、私の経験を基に、医療情報学サイトの収益化を「検討編」としてまとめます。広告掲載後には実践結果も公開予定です。
参考 1. サイトの現状と再検討のきっかけ mic.or.jpは、コンピュータサイエンスやツール紹介を中心にさまざまな気になる事柄の記事を公開・運営してきました。立ち上げから約15年、月間PVは数千〜1万程度で安定していますが、執筆の手間とサーバー維持費の負担が徐々に重くのしかかっています。
これらを踏まえ、収益化を「補助輪」として位置づけ、サイトの質を損なわない形を探ります。医療関連サイトゆえ、広告の選定は特に慎重に—信頼性を守りつつ、運営を楽しく継続したいところです。
2. 収益化のメリット・デメリット分析 収益化の第一歩は、冷静な分析です。私の過去経験と、類似サイトの事例(例: 学術ブログのAdSense導入報告)から、以下のようにまとめます。
メリット:
経済的安定 : 数千円からスタートし、PV増加で月1万円超も現実的。サーバー費やドメイン更新をカバー可能。モチベーション向上 : 収益が見える化され、執筆意欲が持続。読者も「価値あるコンテンツ」として認識。→役に立つ情報公開を中心に据えますが、収益目的重視のコンテンツにはしない方針デメリット:
ユーザー離脱リスク : 広告過多で「商業的」と見なされ、信頼低下。初期労力 : 申請・最適化で1-2週間かかる。収益ゼロの「沈黙期間」も覚悟。収益化検討編の記事公開による影響の推測 以下はGrokによる推測情報: 公開した方が収益は上がる可能性が高い と推測しますが、条件付きで多少のリスクもあります。以下で詳しく説明します。
1. 全体的な影響のメカニズム トラフィック増加の効果(プラス要因) :信頼性とエンゲージメントの向上(プラス要因) :デメリットの可能性(マイナス要因) :2. 収益変動のシナリオ推測(テーブルで比較) 以下は、公開した場合の収益影響を、短期・長期で推測したものです。前提として、広告準備中なので初期PVは低めと仮定(月間1,000〜5,000PV程度)。
シナリオ 短期影響(1〜3ヶ月) 長期影響(6ヶ月以上) 収益変動推測 理由 公開する +10〜30% +20〜50% 上がる 新規検索流入でPV増。Tips記事自体が広告表示機会を生む。事例: 収益化記事公開で月10万円達成。 公開しない ±0% ±0% 変わらない 既存コンテンツ頼みで成長停滞。競合に後れを取る可能性。 公開+数字非公開 +15〜40% +30%以上 大きく上がる リスク低減しつつ信頼獲得。メンテナンス次第で安定。
上がる確率が高い理由 : ブログ/サイト運営の80%以上の事例で、収益化Tips公開がPVを押し上げ、結果として広告収益を増加させています。 特に準備中の広告掲載後([広告掲載後公開]と指定)なら、記事内で広告を自然に紹介でき、コンバージョンも期待できます。下がる可能性は低い : 炎上リスク(例: 誤情報)がない限り、収益減少は稀。むしろ非公開の方が機会損失になります。3. 公開時のTips(収益最大化のために) 記事構成 : 導入部で自身のサイト(mic.or.jp)の事例を軽く触れ、読者の共感を呼ぶ。SEO対策(キーワード: 「医療サイト 収益化」「広告準備 方法」)を入れて検索上位狙い。注意点 : 数字(収益額)は伏せて「検討編」に留め、デメリット記事のようにトラブル避け。 公開後、Google AnalyticsでPV/クリック率を追跡し、調整を。追加推奨 : X(Twitter)で記事をシェアすると、さらなる流入が見込めます。関連議論では、超特化記事が収益安定に効くとあります。全体として、公開をおすすめします。収益化準備中のタイミングでこうした記事は「フック」になりやすく、サイトの成長を加速させるはずです。何か具体的な原稿ドラフトが必要なら、追加で相談してください!
以上が、Grokによる分析結果でした。 実際のところはどうなんでしょうか。
Adsense? 関連記事