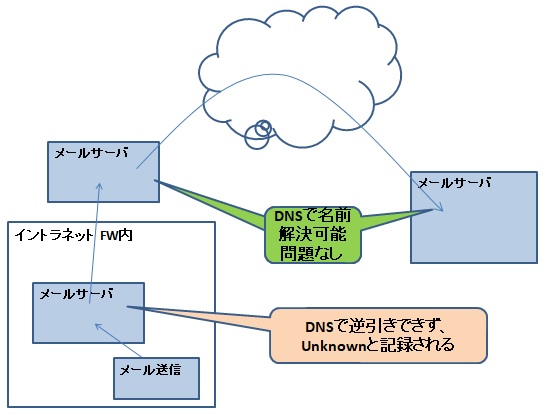2020/4/29にWordPress5.4.1がリリースされました。これには7件のセキュリティ修正が含まれています。ただ相変わらず修正内容に関する情報公開がぬるい。修正のほかに強化項目も含まれているので何用のリリースなのか分かりにくい。
■5.4.1での修正内容は
情報公開で、分かりにくいポイントはいくつかあるが、ぱっと見どれがセキュリティ修正かわからない。NVD、JVNには4/30時点では、まだ情報公開されていないようです。修正内容のほとんどはバグ作り込みが、WP5.4となっています。そして2件の修正対象のバグ作り込みバージョンは5.3となっています。 これはREST APIに関するものです。 この修正では、5.2以前のものはなさそうなので、 5.2系を使っているところは様子見でよさそう。
REST APIの件がセキュリティ修正かどうかが気になる。 #49648はプロパティのアトリビュートが取れない問題、#49645も同様にREST APIを使ったシーンで情報が取れない問題だ。これは、セキュリティかどうかに関係なくアップデートしておいたほうがよさそうです。 アップデートするとなると気になるのは、5.4や5.4.1で強化された項目の残バグの状況です。
■残留バグ、つぎの修正の予定は?
すでに5.4.2を作業中のようです。これも強化を含む修正で、5.1で作り込んだバグの修正も含みそうです。
■それで、どうする?
5.4.1については、 5.3系には適用するのでよいでしょう。 5.2以前は5.4.2が出るのを待つので良いでしょう。5.2は5.2.6が自動適用されました。
それからNVDなどの情報もチェックしましょう。
■追記:5.2.6の内容は?
5.4.1の修正内容ではなく、5.4.2で作業中のテーマの更新を先行して出したようです。WordPressの修正一覧ではマイルストーン、バージョンともに5.2.6はまだ登録されていません。 修正内容もチェックしておきましょう。